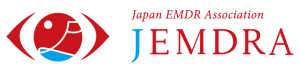ニューズレター36・37号 合併号(2024冬)
ニューズレター36・37号合併号 2024冬号
- 巻頭言 理事長再任あいさつ 市井 雅哉
- 第19回(2024)大会運営印象記 岡田 太陽
- 第19回(2024)継続研修参加印象記 髙田 裕子
- 第19回(2024)大会参加印象記 木下 貴文
- 第18回(2023)大会参加印象記 佐藤 裕美
- 第18回(2023)継続研修参加印象記 森 ゆみ
- EMDR Summit(2023.4, 米国) 白川 美也子
- EMDR Asia(2023.12, カンボジア) 市井 雅哉
- トレーニング参加印象記 Weekend1 城谷 麻衣子
- トレーニング参加印象記 Weekend2 西川 公平
- 地方勉強会参加記(1)佐藤平岡 理子
- 地方勉強会参加記(2)福井 瑞葉
- 臨床家資格保持者に聞く(1)土持 さやか
- 臨床家資格保持者に聞く(2)成井 尚子
- 新理事体制の紹介
- 新理事就任の抱負(1)大塚 美菜子
- 新理事就任の抱負(2)南川 華奈
- お知らせ
- トレーニングについて
- 編集後記
日本EMDR学会理事長 兵庫教育大学
市井 雅哉(いちい まさや)
早いもので、2024年も残り3ヶ月となりました。7月の総会から新理事体制となりましたが、大変ありがたいことに理事長に再任されました。兵庫教育大学退職の日まで残り1年半となり、大学の研究室に置いていた事務局も退官の際には移転を余儀なくされます。社団法人化も控えていて、学会は大きく生まれ変わるタイミングを迎えていると言えましょう。理事のメンバーも新しい人達が新しい風を吹かせてくれることと期待しています。これまで学会の礎を築いて来て頂いた旧理事の先生方にお礼を申し上げます。上田英一郎先生、白川美也子先生、本多正道先生、森本武志先生、幸田有史先生、吉川久史先生、この度監事を退任された太田茂行先生、杉山登志郎先生、ありがとうございました。
先に、MLにも投稿しましたが、令和6年1月26日に発表された中央社会保険医療協議会総会(第581回)の個別改定項目において、「地域移行・地域生活支援の充実を含む質の高い精神医療の評価」の中で、「心理支援加算の新設」として、「心的外傷に起因する症状を有する患者に対して適切な介入を推進する観点から、精神科を担当する医師の指示を受けた公認心理師が必要な支援を行った場合について、新たな評価を行う(下線は筆者)」とされ、保険点数算定(250点)の対象とすることが提言されました。背景には性犯罪被害者の方たちからの悲痛な訴えがあったと聞き及んでいます。点数が十分でないことはもちろん残念なことではありますが、心理士の仕事が健康保険の中で認識をされたことは大きな一歩と考えます。
つい先日締め切った11月のEMDR W1トレーニング(東京)への参加希望者は63名の定員に対して、347名と5倍以上の応募となっています。この背景には心的外傷、それへの適切な介入としてのEMDRへの期待が反映されていると思います。これを「嬉しい悲鳴」というような表現で喜んでいる場合ではないと考えています。このような慢性的に受講したい方が受講までに何年も待たされる状態は解消されるべきものです。武蔵野大学の菊池安希子先生が新しいトレーナーとして来年にはデビュー頂けます。私自身もトレーニングの機会を増やせるように考えています。最近、早河ゆかり先生(はやかわカウンセリングオフィス)、常田修一先生(JA長野厚生連 北信総合病院 心理療法科)、森ゆみ先生(心療内科新クリニック)がファシリテーターになられましたが、さらにファシリテーターを増やしていく必要があります。先日の学会総会の折に、コンサルタントの中からファシリテーターに挑戦頂きたいということをお知らせしました。会員の皆様が、臨床家資格、コンサルタント資格を取られるように研鑽を積んで頂けたらと思っております。
2025年は日本EMDR学会学術大会の第20回記念大会が「これまで」と「これから」というテーマのもと、大阪で開催されます。大会長を務めさせて頂きます。学会の20年の歩みを振り返りつつ、次の10年でどのように大きくなっていくのかを展望できたらと考えています。近々学会員のみなさまにアンケートを取らせて頂いて、ご自身にとってのEMDRの位置づけ、学会への期待などを調査したいと考えています。ご協力をどうぞよろしくお願いします。トラウマに焦点を当てた心理療法は大変多くありますが、エビデンスのある、妥当性があり、侵襲性のより低い心理療法としてのEMDRを次代へと繋いでいくことが責務と考えておりますので、みなさんの現在地点、そして希望を教えて下さい。継続研修は「摂食障害へのEMDR」としてスペインのNatalia Seijo先生に来日頂き、対面で行います。摂食障害は解離、依存、自己イメージ、身体イメージの歪みなどさまざまな問題とも関連した、複雑で難治な疾患です。沢山のヒントが得られると大変楽しみにしています。
本邦におけるエビデンスの確立について、2022〜25年度の4年間で文部科学省の科学研究費を頂き、成人PTSDに対するEMDRの有効性を検討する研究を行っています。研究チームには、清章福祉会の天野玉記先生、長崎大学の今村明先生、大阪医科薬科大学の上田英一郎先生、金沢徹文先生、武蔵野大学の菊池安希子先生、福井大学の小坂浩隆先生、神戸親和大学の椎野智子先生、甲南大学の前田多章先生に入って頂いております。そして、長崎の心療内科新クリニックの院長森貴俊先生、心理士久冨香苗先生、上野久美子先生、大阪医科薬科大学の川端康雄先生のご協力の元順調にデータを収集しているところです。研究拠点の2カ所の近隣の先生方にはご協力をお願いしておりますが、患者様をご紹介頂いた先生方どうもありがとうございます。今しばらくご紹介をどうぞよろしくお願いします。
付記:新理事の早河ゆかり先生がご都合により辞任され、次点からの繰り上がりで沖縄の松本大進先生(カウンセリングオフィス-misora-)が就任されました。どうぞよろしくお願いします。
日本EMDR学会第19回大会大会長
カウンセリングルームCircle of Life (サークル オブ ライフ)
岡田 太陽(おかだ たいよう)
2024年7月に開催された日本EMDR学会第19回大会の大会長を務めさせていただきました。改めましてみなさまご参加いただきありがとうございました。
学術大会では準備委員会に労いのお言葉を多く頂戴しましたが、EMDR学会事務局の小池さんとG-ONE株式会社の須田さんはじめスタッフのみなさまのご助力なしには成功し得ませんでした。本当に感謝しております。当日の運営には会場でもある明治大学の学生さん達に本当に助けていただきました。合わせてここに感謝を述べさせていただきます。
今大会、大会テーマには「ダイバーシティ」と「持続可能性」への挑戦も含んでおりました。そのため準備委員会もできるだけ省エネにし、「持続可能性」について挑戦してみました。実は今大会の準備委員会はオンラインで2回しか開催しておりません。メンバーの顔合わせとテーマ決めで1回。もう1回は当日の役割分担で1回という感じです。もちろん都度都度準備委員会のメンバーに個別に協力をお願いしていましたし、メールで進捗を伝えたり相談したりはしていますが、骨子はほぼ副大会長との二人三脚で作り上げてきました。なお、ここには継続研修会の講師との交渉も含まれます。
「歴戦のメンバーだからできたことでしょ?」というご意見もあるかもしれませんが、今大会、何より大きいのはチームに「パワー」が存在せず、代わりに「仲の良さ」で運営した準備委員会だったからできたことだと思います。
継続研修会の講師を探すのも思いがけず難航しました。Laura Parnell先生、Shirley Jean Schmidt先生、Anabel Gonzalez先生、Debra Wesselmann先生などを検討しましたが、「大会長が招聘する好きな先生を決めてもいい」と言われていてもやはり様々なご意見もあり・・・。最終的に昨年の継続研修会の講師でもあるSandra Paulsen先生に「ヨーロッパの神経発達症の子どもへのEMDRの専門家をご紹介いただけないか?」とお願いし、今大会の継続研修会の講師であるSusan Darker-Smith先生をご紹介いただきました。ご紹介いただいたもののSandra先生も直接面識があるわけではないようでしたので、Susan先生の公開されている連絡先に無理を承知で継続研修会の講師のお願いをしたのが昨年の11月。その日中にSusan先生からお引き受けいたしますとのお返事をいただきました。面識も全くない遠い国の人間からのお願いにも関わらず快くお引き受けくださったSusan先生には感謝しかありません。
EMDR学会では第13・15・16・18回と4大会かけて弁護士による倫理についての教育講演が行われてきました。参加者としてその内容を拝聴し、非常に興味深い内容ではありましたが、その一方で「法律という枠組みから倫理のあり方を問うやり方はちょっと違うのでは?」と思っていました。特別講演に「特権」の専門家である出口真紀子先生にお願いしたのは、もっと等しく参加者みんなで「特権」について考え「心地悪さ」を感じたい・・・そう思ったからです。
記念大会となる第20回大会に新しいスタートを切ることができるように、今大会ではしっかり「あり方」を問いかけ、考えたい。大会長としてのその思いが参加者のみなさまに少しでも伝わっていたら幸いです。
最後になりましたが、今大会1・2号通信の作成、申し込みフォーム、BASEショップ作成など窓口の多くを私が担当させていただいておりました。事務局の小池さんの指示もあり、注意事項はできるだけ書くようにしておりましたが、非常に多くの方からの誤入力、重複申し込み、書いてあることについてのお問い合わせをいただきました。その量のあまりの多さにびっくりした次第です。みなさまお忙しいとは思いますが、今後できる限り注意事項などしっかり読んでからの入力お願いします。また、今大会申し込み時に守秘義務遵守のお願いをさせていただいておりましたが、それでもなお悲しいことにSNSにて危うい投稿をされている方を拝見しました(既に削除されていますが)。私が言うことではないかもしれませんが、SNS(特にオープンアカウント)での発言にはくれぐれもご注意をお願いします。
今大会をきっかけとして、引き続きみなさまがそれぞれの「あり方」について深く考えていってくださることを望んでおります。ありがとうございました。
しがカウンセリングルーム Resource-リソース-
髙田 裕子(たかた ゆうこ)
第19回継続研修は、2024年7月27日(土)と28日(日)の2日間に渡り、Web開催で行われました。講師は日本EMDR学会継続研修では初めてのご講演となるEMDR Europe公認Child & Adolescent TrainingのトレーナーおよびコンサルタントであるSusan M. Darker-Smith先生です。本研修の主題は「ADHDやASDといった神経多様性の特徴を持つ子どもへのEMDR」で、私にとって最も必要性が高く心待ちにしていた内容でした。
1日目の主なテーマは、脳の違いの理解、神経多様な脳のトラウマ、神経多様な脳を理解こと、「S.C.O.T」、EMDRフォーミュレーションでした。2日目のテーマは、「S.C.O.T」の実演、AIPレンズを通した神経多様性、神経多様な脳を持つクライエントへのEMDRの第1段階と第2段階、STARTモデル、第3段階から第8段階、標準プロトコルの代替(箱庭)、ナラティブについてです。
特に私にとって貴重な学びの機会となったのは、「S.C.O.T」の実演でした。この概念は、1日目の後半に講義があり、Th.がCl.との治療における「S=Strengths(強み)」「C=Challenges(チャレンジ)」「O=Opportunities(機会)」「T=Threats(脅威)」を見出しながら作成します。Susan先生が「S.C.O.T」を考案された由来や意図等を説明され、架空事例として自閉症、ADHD、ディスレクシアの子どもについて、3事例を「S.C.O.T」でご提示いただきました。
その後、数人ずつブレイクアウトルームに分かれて「S.C.O.T」の演習を行いました。参加者は、Cl.役、Th.役、Obs.役に分かれ、私はCl.役を担当しました。私は学校現場で出会うことのある、自閉スペクトラム症、ADHD、ディスクレシアがあるCl.をそれぞれ想定しロールプレイを行いました。演習ではCl.役とTh.役のロールプレイを基にグループ全員で「S.C.O.T」を作成する予定でしたが、チャレンジと脅威は出てくるものの、強みと機会が見出せないまま終了しました。同じグループのObs.役が、Susan先生に「強みと機会が出てこない」と質問すると、2日目はその「S.C.O.T」の実演から始めることになりました。

2日目の開始時、270名を超えるEMDRセラピストの研修受講者の前で、私は架空Cl.の事例を提示し、Susan先生に「S.C.O.T」の実演をしていただく貴重な機会を得ました。Susan先生の実演では、Cl.の特徴が全体像として繋がり、ネガティブな特徴がポジティブな表現に変容する重要性を学びました。講義の中でも「Cl.が教えてくれる」「Cl.から学ぶ」とお話しされる様子は、私がCl.の特徴を話すたびに、聞き手がその状況をリアルに想像できるものでした。
Susan先生が示した多くの強みと機会により、私の臨床も「S・C・O・T」を活用する日々へと変わりました。「ボディソックス」や「ぐらぐらボード」などは、私の臨床アイテムとしても欠かせないものとなっています。EMDR治療を取り入れることが難しいセラピーを、円滑に進める様々なお話をいただいたSusan先生に深謝いたします。また大会準備委員の皆さま、通訳の大澤智子先生と菊池安希子先生、そしてEMDR治療の普及活動にご尽力いただいている先生方に心より御礼申し上げます。
こころとからだ・光の花クリニック
木下 貴文(きのした たかふみ)
EMDR学会は去年に続き2回目の参加です。必要に迫られて数年前からTSPを中心にトラウマ臨床に取り組んできましたが、今年ようやくWeekend1に参加でき、治療技法の基本形や機序を改めて学び中です。多くの臨床例に触れる中で、各種トラウマ処理技法がうまく導入できず、また定型的に実施しても改善しないケースに一定数遭遇しますが、おそらく技法の問題より治療関係、アセスメント、安定化の段階などを見直すべきと感じていました。<技法の手前のセラピストとしてのあり方>という学会テーマは、自分にとってタイムリーで、とても有意義な一日になりました。以下駆け足で紹介してみます:
岡田先生の大会長講演では、神経発達症など言語的なやり取りが苦手な子どもに対して、セラピーカードの活用が提案されました。標準的なEMDRはNCやPCの扱いなど認知的側面が強く一定の知的水準を要求する印象がありますが、カードやイメージ・メタファーを活用して本人の「ファンタスティック・リアリティ」の世界を扱うことで、より多くの方に治療導入でき、また治療の中に楽しさや双方向性を導入しやすそうで、子どもに限らずに試してみたいと感じました。
続く午前中は2つの症例提示を続けて聞きました。神村先生の中学生の症例ではTSP、自我状態療法で比較的短期間の改善をみており、治療初期の丁寧な心理教育と安定化の部分が特に参考になりました。もう一つは原賀先生の、解離・逸脱行為・家族関係の問題等がある、高校生の難しい症例でした。数年で次第に改善する経過は感動的でもあり、治療関係や治療方法の工夫も素晴らしいですが、数年間の治療を継続できた事に「運命的」とも形容できる驚きを覚えました。どちらの症例も十分なディスカッションの時間があればより深められたのにと少し残念でした。
昼休みには総会に初めて参加し、学会運営について、初期の小規模で属人性が強い形態から、大組織・集団的コントロールへの移行期であると想像しました。一般的にこの時期の中長期的な舵取りは様々な難しい点があり、(他人事のようで申し訳ないですが)新しい役員の先生方は大変だなあと思いました。
午後1つ目は杉山先生の、自我状態療法上における工夫(お稲荷さん)についてでした。個人的経験からDID臨床では宗教的・実存的なテーマに触れざるを得ないと考えるのですが、日本の文脈では仏教系より神社系の方がリソースとして使いやすく感じており、具体例として興味深く拝聴しました。また質疑応答を通して、杉山先生の独特な臨床スタイルが垣間見えた点も印象的でした。
午後2つ目は準備段階と安定化のシンポジウムでした。3人の先生方のお話から多数の貴重なヒントを得た一方で、「総論✕3」よりもっと各論を聞きたい!とも感じました。臨床で出会う患者さんの多くが標準的なトラウマ処理技法をそのまま適用できない中で個々の支援者がこの段階を個別に工夫している状況がありそうで、この段階についての教科書やパッケージ治療等がある事が望ましく、関連学会が公的に取り組むべき課題なのでは、と考えました。
最後の出口先生の特別講演は、フェミニズム・批判理論の立場から、規範概念としての「特権」について概説なさったものと思われました。たとえば「男性・医師」である事は診察室内で「特権」として作用する。私達に馴染みがある文脈では、治療構造論や転移概念として検討されてきたことや、治療場面での双方のトラウマ反応にも関わりそうですが、出口先生の講義とはミクローマクロの分析レベルが異なっており、双方向の対話がしてみたい、と思わせる内容でした。
社会医療法人公徳会 佐藤病院
佐藤 裕美(さとう ゆみ)
はじめに、今回はDVDでの参加印象記となることをおゆるしください。
コロナ禍で2020年の第15回大会からオンラインでの開催が続き、誰もが再び対面開催で集える日を心待ちにしていました。そして、2023年の第18回大会は、4年ぶりの対面開催となり、大会テーマの通り「再びつながる」ことができた大会だったのではないかと思います。
私も対面で大会に参加できる日を心待ちにしていた一人でした。しかし、遠方に住んでいるため、関西での大会には、今回だけでなく、これまでも参加が叶いませんでした。2018年にサンドラ・ポールセン先生の継続研修が関西で開催された時も、私は涙を飲んで参加を断念していました。
ところが今回、サンドラ先生の継続研修が再び開催され、その上、DVDが販売されることとなり、私にとっては夢のような話でした。大会の第一報を見ながら、大会テーマである「再びつながる」とは、今ここで私に起きていることではないだろうかと勝手な解釈をし、迷うことなくDVDの購入を申し込みました。
学術大会では、様々な臨床実践、法的問題、トラウマをめぐるモデル、脳神経学と多岐にわたる発表があり、いずれも興味深いものでした。特に、名和淳先生が深刻な解離のあるクライエントへの関わりから「セラピストは決して孤軍奮闘するのではない」「様々な地域や治療のシステム、クライエントの内的システムがあるからこそ、セラピストは支えられ、クライエントを支えることができる」と述べられていたことがとても印象深く、私自身も日々の臨床の中で様々なシステムとのつながりに支えられていることに気づかされました。
宮地尚子先生の招待講演では、トラウマの環状島モデルから、トラウマをもつ当事者と支援者の立ち位置や関係性、起きていることの全体像を理解する新しい視座をいただきました。
脳神経学のシンポジウムでは、普段聞き慣れない単語が洪水のように私に襲い掛かってきたため、必死で何かをつかみとろうとした結果、30回以上DVDを再生することになりました。前田多章先生は記憶の仕組みや睡眠との関連についてわかりやすくご講義くださり、EMDRの脳への作用モデルも示してくだいました。企画者の天野玉記先生からの補足も受け、脳の観点からEMDRで記憶にどの程度の時間、どのようにアクセスすると良いのか等が理解できたときには、見える世界が変わったような感覚をおぼえました。しかし、これらの学びも時間が経つと思い出せなくなるので、この印象記を書いている2024年10月現在も、DVDを見返しては再生回数の記録を更新し続けています。そのようなことから、今回は心底DVDを購入して良かったと感じているところです。
サンドラ先生の継続研修では、情動回路のリセットと早期トラウマアプローチを学ぶことができ、長年の悲願を成就したような思いでした。DVD視聴のためワークには参加できませんでしたが、自我状態との関わり方や愛着の修復についても具体的なイメージをつかむことができました。
DVDの最後には、大会長の海野千畝子先生がねばってくださったことで、再びサンドラ先生の研修が実現したことが明かされていました。海野先生には心より感謝を申し上げます。そして大会を準備してくださった先生方、いつもわかりやすく温かみのある通訳をしてくださる菊地安希子先生と大澤智子先生にも心より御礼を申し上げます。
医療法人 心療内科 新クリニック
森 ゆみ(もり ゆみ)
第18回継続研修会は、眩しすぎるくらいの陽光が降り注ぐ2023年7月の神戸にて、Sandra Paulsen (サンドラ・ポールセン)博士をお招きし、2日間にわたって行われました。
久しぶりの対面、しかも外国人講師を目の前にしての開催です。もちろんまだこの頃は、馴染みの場所に向かう道すがら、あったはずの自販機が撤去されていたり、使えたはずの駐車場が閉鎖されていたりと、街には、時を止めざるを得なかった期間の余波を感じるところもありました。しかし実際の会場では、快適なポジションを求めての座席の厳選や、思いがけず出会えた相手に出てしまう小さな感激の声など、かつての当たり前であった動作や出来事に遭遇する度に、その新鮮さや喜びに心が動かされるような光景が広がっていたかと思います。
研修会初日の夜は、懇親会も催されました。和を意識した、幻想的な舞や珍しい楽器の演奏に華を添えてもらい、博士や前日の学術大会にご登壇いただいた宮地先生をも囲み、円卓での食事や写真撮影が行われました。以前と変わらぬ情景であったとはいえ、いつもよりも上気していたのでしょう。打ち合わせたわけでもないのに、最後には自然と高音や低音のパートに分かれての「ふるさと」の大合唱。居合わせた皆は、自ら発する声が、他者のそれと交わり合いながら、ふくよかなハーモニーへと厚みを増していき、更には四面にこだまして跳ね返ってくる微細な振動をも楽しみながら、共に時を過ごしました。
さて肝心の研修についても触れなくてはなりません。博士が考案したNESTの技法は、人生早期のトラウマや、ネグレクトを含む複雑なケースに対し、EMDRや身体療法、自我状態療法などを統合することで、解決への道筋を見いだしていくものです。「これらN・E・S・Tのそれぞれを取り上げただけでも、4つのワークショップができてしまう」膨大な情報量の中から、本研修は、最も重要な部分を凝縮し網羅したものを2日間で学ぶことができるという、盛りだくさん、且つ贅沢な内容で構成されていました。
「再びつながる」をテーマに掲げた本大会でしたが、博士と「再びつながる」参加者の先生方も多かったことと思います。「パンセック感情回路のリセット」については、より詳しい理論を求める質問や、使用してみての所感など、「再びつながる」からこそ尋ねられる話題が積極的に述べられ、以前に増しての議論の盛り上がりや深まりが感じられました。また、ひょんなことから特別に教えていただいた、「タヌキ薬」「オオカミ薬」といった、編み込みにも使える技法のエクササイズでは、舞台上にて全身でお手本を示す博士に倣い、皆が一様に同じ動作に取り組みました。その結果、全体ワークの際に生まれる、場の佇まいや久しぶりの肌感覚へも「再びつながる」ことができ、笑顔の博士からは「会場のエネルギーに一貫性がもたらされましたね」とのご感想をいただきました。
このように書き記していると、当時の学びの内容は言うまでもなく、ホールに響くざわめきや笑い声、好奇心に比例して自然と伸びる各々の背筋、所々での感嘆のため息になぜか感じる色味など、お伝えしたいことの中核には、あらゆる言葉を尽くしたところで、そもそもが書き表せない、「言葉にならないもの」が、数多く大きく存在していることに気づかされます。この原稿にて、それらがどこまで表現できたかは定かではありませんが、ご参加いただいた先生方には、その時の熱気や高揚感に「再びつながる」、あるいは来場が叶わなかった先生方には、抱かれた興味や関心がより深い知識へと「再びつながる」、といったお手伝いが出来ておりましたら幸いです。
こころとからだ・光の花クリニック
白川 美也子(しらかわ みやこ)
2024年4月18日~29日、前日のトレーナー及びコンサルタントデイを含めると4日間、米国ワシントン州ベルビューにて、EMDRIA Summit 2024が開催されました。私はワシントシン州シアトルに長期滞在しながら、ベインブリッジ島にお住まいのSandra Paulsen博士を訪問したりしている折、市井雅哉理事長から情報をいただき、思いがけず参加することができました。
学会の朝は早く、朝7時の朝ヨガから始まり、さまざまな団体のブースが出店されている会場での美味しい朝食、その後、一般、分科会、体験セッション、SIG meeting(Special Interest Group)が会場ごとに行われていきます。内容は現在は以下EMDRIAのHPで見ることができますが[1]、資料として3日間の内容の概要として大会場で行われた2つの一般セッションと分科会の内容を紹介します。
一つ目は「セラピストである人間のための解放的でトラウマレスポンシブで交差的なセルフケア」
フェミニストセラピストとして著名なLaura Brown博士が、
自分自身の交差性(人種、階級、ジェンダー、セクシュアリティ、国籍、世代、能力などのカテゴリーが相互に関係し、人の経験を形づくっていることを示す概念)を明かしながら、トラウマワーカーの立場性や辺境性、トラウマセラピストのセルフケアの必要性とその本質などについてのプレゼンテーションでした。「セルフケアとは、ネイルをしたり、短い旅をしたりすることではない。トラウマに悩まされ苦しんでいる人たちと仕事をする私たちの自分自身と魂へのケアが必須であることに気づくこと。それがなければ、この仕事を倫理的にうまく遂行する能力が損なわれ、燃えあがってしまうのです」。燃え尽きを経験し渡米した自分の心身に沁みました。
二つ目は「複雑なトラウマの癒しにおけるEMDRの影響: 安定化から再処理へ」
日本のEMDRセラピストにも馴染みの深いDolores Mosquera先生の複雑性PTSD(解離症スペクトラム)の安定化から再処理に至るまでのいつもながらのクリアカットなプレゼンテーションでした。
分科会は15演題、いずれも症例研究レベルではない本格的な教育プレゼンテーションです。テーマの一部を羅列すると、児童期の性的虐待、依存症、子どもの解離、多様性・公平性・包括性・正義などの問題、サイケデリック・アシステッド・セラピー、不安障害、ソマティック・アプローチ、発達性トラウマを受けた子ども、摂食障害、表現芸術、障害に関わる交差性、悲嘆後の脳の再調整、倫理、自殺予防、複雑なトラウマ症例、身体性の実践、文化的トラウマと逆境を含む症例の概念化など多様です。

どのセッションも一人の海外講師を呼ぶ重量に近い内容です。各講師による自分のセッションの紹介は現在でもYoutubeでも見ることができます。15本ありますので、興味ある方はぜひご覧ください[2]。
日本からの参加者は一人でしたが、Sandra先生と彼女が繋がっているカナダのセラピスト、Ana Gomez先生、初期にDIDへのEMDRについて教えてくださったCurt Rouanzoin先生、他のEMDRIAトレーナーの方たちなどと親しくお話をすることができました。Francine Shapiroの逝去から5年経ちましたが、トラウマを受けた方達を支えるセラピストに蒔かれた「奇妙な種」は、さまざまなところで花を咲かせています。写真は会場を出る時に配布されたジグソーパズルのピースに書いた「私にとってのEMDR」の写真です。会場で出会った笑顔あふれるEMDRセラピストとの交流が鮮やかに記憶に浮かんできます。
[1] https://emdriasummit.com (2024.10.7確認)[2] General Session 101 Liberatory Trauma Responsive Intersectional Self Care for Humans Therapists E(2024.10.7確認)
日本EMDR学会理事長
兵庫教育大学
市井 雅哉(いちい まさや)
2023年12月15‐17日「EMDR療法、希望の再構築」のテーマの元、第5回EMDRアジア会議がカンボジア、シェムリアップで開催されました。年末の忙しい時期、今回は私以外の日本人参加者が一人のみという寂しさでしたが、日本の冬の時期、赤道も近い真夏のシェムリアップに行って参りました。
プリコンファレンスワークショップ「EMDR療法における社会的および文化的関連トラウマと逆境」マーク・ニッカーソン博士(米)、「EMDRアジア実務家にとっての実践的な課題と文化的意味合い」デボラ・シルベリア博士(米)、ミシェル・ゴットリーブ博士(米)、ドゥシャイアント・バドリカー博士(印)、ジンソン・チャン博士(中国)。
パネルディスカッション1「トラウマ回復ネットワーク-災害対応のためのコミュニティアウトリーチ」、パネルディスカッション2「スピリチュアリティとEMDR」。
基調講演はキャロル・マーティン博士(米)の「アジアにおける希望の再構築と共同の取り組み」、デレク・ファレル博士(英)の「適応情報処理のレンズを通して道徳的トラウマ/傷害を理解する:概念的枠組みと治療介入」。
特別セッションはドロレス・モスケラ博士(スペイン)「解離性障害におけるトラウマ記憶の安定化から処理への安全な移行:マイクロ処理手順」、「EMDRによるソマトフォーム解離の治療」、ゲイリー・クイン博士(イスラエル)「過去、現在、および将来の災害と修正された簡単なEMDR介入」がありました。
世界的に多様性への理解が進んでいる印象の昨今ですが、特に、アジアの文化的特殊性、スピリチャリティなどへの理解、配慮が色濃く感じられた大会でした。日本はそういう意味では随分と欧米化していると改めて感じました。個別のケース発表で、パキスタンの人たち(Rusham Zahra Ranaによる慢性疼痛へのアプローチ)の発表のレベルが高かったのが印象的でした。時々は会場を抜け出して、アンコールワットなどの遺跡群も存分に楽しみました。地雷で足を失くした方がグループで音楽を奏でて生計を立てている姿は物悲しかったです。幼い頃の京都河原町辺りの景色を思い出しました。
皆様から頂いた寄付金460,326円もしっかりと届けさせて頂き、大会運営のために役立てて頂いたことも申し添えておきます。
次の第6回は2026年1月30日‐2月1日インドのムンバイで行われます。

EMDRトレーニングを終え、今、感じていること
医療法人緑光会 城谷病院
城谷 麻衣子(じょうや まいこ)
皆さん初めまして。城谷(じょうや)麻衣子と申します。今年3月、EMDRweekend1のトレーニングを修了し、この度、体験記の御用命をいただきました。普段私は、長崎県の諫早市という長閑な田舎の精神科病院で外来と入院の患者様の診療を行っていて、月一度は長崎市の相談センターの女性支援課にて嘱託医をしています。診療の中で様々な疾患・状態像の背景にトラウマが強くかかわっているようなケースも多く、色々とトラウマ治療に関する勉強をしてきましたが、今回ようやく機に恵まれEMDRの研修を受けることができました。
2024年3月、神戸市の三宮研修センターWeekend1初日。当日の会場は、満を持して参加の皆さんの熱量と緊張感に満ちていましたが、市井先生の都道府県アンケートが行われ、北から南まで多くの治療者がいて、大変な治療に携わっているのだとわかり、なんだか勝手に連帯感を感じておりました。講義では、冒頭の方で、EMDRの誕生について、ベトナム戦争帰還兵の戦争トラウマ治療の体験から「R=reprocessing」の部分、つまり「単なる脱感作ではなく再処理が意味の変容をもたらす」という気付きがあり、それが元となって今のEMDRの形が作られてきたという話を伺って、これが治療の原理を理解するのにとても役立ちました。また、治療のビデオの視聴では、「クライアント自身がどのように変化していくか」「その場にセラピストはどのように存在しているのか」という、言葉では説明が難しい部分を見て学び、また、その中でその治療過程の温かみやその力強さの様なものを感じ取ったことで、EMDRというものに対するイメージがガラリと変わった気がします。(weekend2でもう一度観たときは、また別の視点からの気づきが増えて新鮮な気持ちで拝見しました。)また、実習では特にクライアント役でEMDRで何が起こるかということを自ら体験することになり、これもとても重要で欠かせないステップであったと思います。
10月にはweekend2の研修を修了し、少しずつ患者さんに治療を提供する機会も増えてくる中で、まだ難しい点も多く四苦八苦していますが、それでも、患者さん自身からみられる変化や力に驚くことも多々あり、治療者としての深い喜びを感じます。治療において、まだEMDRを用いていない場合や第1段階や準備段階のときでも、いわゆるAIPモデルや、過去・現在・未来モデルでその人を理解するようになるので、そのことが治療の流れや治療関係に良い影響を与えているのかもしれません。
EMDR研修を終え、今はまだスタート地点に立ったばかりの私ですが、治療を実践し、書籍などを読み勉強する中で、EMDRは単なる治療法というよりも、トラウマとその治療について学ぶための重要な基本的理論であり、またこれから先も育てられ進化していくものだということが、少しずつですが見えてきました。
複雑化したトラウマを抱えた方との関わりでは、時に治療者としての無力さを感じてしまうことも少なくありません。しかし、我々生きものはみんな昔から(鳴き)声を交わしたり、触れ合ったりし、お互いの生命力を分かち合いながら生き延びてきた。そのことに気がつくと、改めてその力を使いこなすことによって、存在と存在の間で何かが起こり、新たに小さな変化を起こし始め、それがいつか大きな力になるかもしれない、と、最近はそんな風に考えています。
最後になりましたが研修会場・コンサルテーションでのご指導に携わっていただいたすべての先生方に、この場を借りて深く感謝を申し上げます。
今後ともどうぞ、よろしくお願いいたします。
CBTセンター/一般社団法人CBT研究所
西川 公平(にしかわ こうへい)
普段から認知行動療法を主たる技法として使っている私は、トラウマ関連技法としては、Prolonged Exposure(PE)、Cognitive Processing Therapy (CPT)、自我状態療法、ホログラフィートークに続いて、EMDRが5つ目の技法だ。なるべくエビデンスがハッキリあるものを習得しようと思っているが、なかなか学ぶ機会が訪れなかったEMDR。厳選なる抽選の結果ついに習う機会が訪れた。私は習った技法は何でもすぐ使う派なので、Weekend1からそんなに期間を開けずに受けられよかった。
研修3日間ではそれぞれ午前が講義で午後が実習と、学ぶと習うがバランスよく配置されていて、さらに間をおいてグループスーパービジョンが入っているなど、長年かけて練られてきた研修/ワークショップだなと思った。トラウマ技法を学ぶのみならず、自営業として研修を主催していくうえでも、色々と参考になる組み立て方だと思った。
講義の部分ではトラウマを扱っていくうえで基本的な事柄や態度を講師の市井先生の豊富な臨床経験から伺うことができて、技法に熟達して楽しそうに使いこなせててとても良いなと思った。
グループでの実習は時間的にタイトスケジュールながらとても楽しく、全員が熱心にこの技法をモノにしようと真剣に取り組んでいたのが印象的だった。貧乏性の私としても決して安くはない研修代の元を取るつもりで、これまた真剣に取り組んだ。実際の所、滋賀に帰ったらすぐさまEMDR使うつもりの数ケースが控えてもいたので、習得のモチベーションも十分にあった。自分が施術を受ける側の感想としては、これまでの人生で傷ついたり腹立ったりしたことを丁寧に扱ってもらえて、なかなかそんな話をできる場もないので、とても新鮮な気分だった。トラウマが処理できるできないに関わらず、正当に扱ってもらえない事柄をきちんと扱ってもらえるというだけでも、共通因子的な治療効果があるんだろうなと思いながら、目を動かしていた。
EMDR界隈には知り合いもほとんどいないので、隣りに座った人とか、一緒のグループだった人とか、エレベーターで乗り合わせた人などに声をかけて、適当な飲み会をしたのも楽しかった。心理の世界は狭いので、すぐに知り合いの知り合いにぶつかるから、なんとでも共通の話題はあるものだ。
私にとって心理の技法とは駒落ちのような「ハンデ戦」で、ルールに沿って、自由にできない分、アレコレ窮屈だ。でも、普段ならやらないようなこと、しないような言葉かけ、登ったことのないルートで臨床の山を登ることで、いつもとは違った景色が見えてくることはままある。今後EMDRが魅せてくれる臨床の景色が楽しいものになると良いなとウキウキしながら研修を終えた。
関西@心理臨床を学ぶ会に参加して
三家クリニック、神戸女子大学臨床心理センター
平岡(佐藤) 理子(ひらおかさとう まさこ)
2023年12月23日大阪大学中之島センターにて開催された第2回「関西@心理臨床を学ぶ会」に参加しました。
テーマは「トラウマ臨床の現在Ⅰ-EMDRその2」であり、内容は市井雅哉先生による「EMDRの基礎と実際」と椎野智子先生による「EMDRの脳科学研究」でした。
事前の案内から、TIC(トラウマ・インフォームド・ケア)やACE研究に代表されるようにトラウマへの理解が重要とされる現在「確かに『車の構造を知らなくても車の運転はできる』が『それを知った上で、より安全で効率的な運転を』という思い」で企画されたと拝見しました。
数年前に基礎資格を取得したものの育児等に追われていた私は、なかなかEMDRに専念出来ない環境の中で、ペーパードライバーに近い状態で不安な中を過ごしてきました。案内から本セミナーで何かをつかめそうな予感を感じてすぐに申込しました。
セミナーはその期待に充分に応えて下さる内容でした。EMDR基礎から実践、さらに『車の構造』である脳科学の知見まで1日で体験することができ、EMDRの効果を確かな希望をもって感じることができました。
この豪華な両先生のコラボ企画は、既に第1回目が関西にて開催されていましたが、多くのリクエストがあり、主催者である中西先生のご尽力により第二弾開催の運びとなりました。そのため初回を逃した私もようやく参加することができました。今回参加した一受講者として感想を記したいと思います。
Ⅰ.「EMDRの基礎と実際」市井雅哉先生
EMDRの概要と、世界や日本で蓄積された知見の紹介、さらに動画を用いた事例提示がありました。
講義や動画のセッションを通して、これまでEMDRを牽引して来られた先生方がEMDRに長年熱意を持って向き合い、臨床に用いて、実際に効果を発揮している力強い姿に改めて勇気づけられました。
また、イメージが目前に浮かぶような例を用いた説明(ACE Studyのリンゴの木、適応的情報処理のベルトコンベア等)は、初学者である私にも理解しやすいものでした。さらに、理解を深めた上で、臨床場面でも生かしていきたいと感じました。
その後のRDI実習も大変貴重な体験となりました。私自身のリソースを発見することができて、セミナーを終えてからは、日常生活での視点に変化が生じ、周囲に対して当然あるものから、有難い感謝として気づけるようになりました。
Ⅱ.「EMDRの脳科学研究」椎野智子先生
初めに、トラウマ体験による脳への深刻な構造的・機能的影響や、健康や寿命への影響(ACE Study)の説明があり、さらに忘れてはいけないこととして、その背景にある社会情勢や世代間トラウマの存在が示されました。
また、過去の研究から、EMDRやPE、TF-CBTなどのトラウマ治療実施後は、脳に肯定的な構造的・機能的変化が生じるだけでなく、さらに、驚くべきことに遺伝子レベルのエピジェネティックな変化をもたらすとの知見を示されました。
私の医学的な知識不足から完全に正しく把握できたとは言い難いですが、日々の臨床に向き合うための脳科学的な根拠を得て、EMDRによるトラウマ治療の効果に改めて勇気付けられました。
また実習や研修全体を通して、参加者同士が試行錯誤しながら互いに協力して関わることにより、臨床家として真摯に学ぼうとする姿勢や、他者に対する暖かさ、その絆を改めて強く感じる機会となりました。
末尾になりましたが、このような充実したセミナーを企画してくださり、当日も丁寧な心遣いをいただいた中西心療内科・内科医院の中西善久先生やスタッフの方々に、心より感謝申し上げます。
強迫性治療の専門家・ブーム博士の講演会を聞いて
カウンセリングルームセコイア
福井 瑞葉(ふくい みずは)
2024年5月20日,東京にて,強迫症治療の専門家であるカルステン・ブーム博士の講演会が開催されました。本講演会は,同年3月20日に神戸で行われた講演のアンコール企画でした。神戸での開催は,兵庫教育大学大学院の市井ゼミに所属していたご縁で,私としては初めて講演会の企画に関わらせていただきました。その時は,まさかブーム博士と市井先生が何気なく「またやろうよ!」と言っていたことが,まさか実現するとは思いもしませんでした。これも,ブーム博士が好奇心旺盛かつユニークな方で,なんと日本に3か月にわたって滞在していたからこそのことです。いわゆる観光旅行ではなく,レンタカーを借りて放浪したり,山に登ったり,都会よりも自然や地域独自の文化を愛する方ということを企画の会話の中で知りました。滞在中,一緒に旅行されていた奥様が「きびだんご」をいたく気に入り,「きびだんご」の歌を自作して歌っていたそうです。
ブーム博士の講演会は,クライエントとの関係性構築の話からはじまりました。博士は,少なくとも5セッションはクライエント理解に費やすそうです。私だったら,強迫症のクライエントには,症状を軽減させるためにホームワークを出すなどの介入をしたくなります。また,強迫症専門家のブーム博士に対して,クライエントは「どうしたら良くなるか」を初回から聞いてくることが多いそうです。まさに,私もそのクライエントと同じく,強迫症治療に特化したEMDRのプロトコルを教えてもらえるんだ!それを使えば強迫症のクライエントに対応できるかもしれない!と問題解決を急いていました。しかし,ブーム博士は臨床の基本の基本がいかに大切かを,人間の尊厳に焦点を当てながら語りました。クライエントを強迫症患者という型にはめるのではなく,「実際の様子を見せてください」と洗浄の様子を実演してもらったり,自宅の写真を持ってきてもらって一緒に眺めたり,可能な限り状況を具体的に描写してもらい,一人の人間としてどんなことに苦しんでいるのかを共有することが最も重要だ,と教えてくれました。
EMDRのデモンストレーションでも,クライエントとともに目の前の現実に取り組む姿が示されました。ブーム博士とクライエント役の方とが一緒になって,汚れた(と思われる)手で,頭や顔を含めて全身をなで回すように触る様子は衝撃的でした。セラピストが身体を張ってモデリングしながら,SUDや身体感覚を確認し,慎重に曝露をすすめ,その後はじめて両側性刺激を用いており,改めてEMDRのプロトコルが準備から始まる意義を知るに至りました。また,面接において,強迫傾向のあるクライエントだからこそ,セラピストは完璧であろうとする必要はなく,むしろ失敗してもいいんだ,という姿をモデリングすることも治療的である,という点は非常に納得できるもので,臨床実践を始めたばかりの私は力がふっと抜ける感覚を得ました。
そのクリエイティブなEMDRの手順はもちろんのこと,参加者からの「ため込み症」の質問や終了後の個別質問に丁寧に答えていらっしゃるブーム博士のお人柄に魅了された方は多いのではないでしょうか。現在,博士はウクライナやイスラエルでトレーニングを精力的に行っているとのことです。人間の尊厳を守ろうという博士の姿勢に私は心から惚れてしまいました。来年にはブーム博士によるグループスーパーヴィジョンを企画しております。ご案内は後日となりますが,みなさま奮ってご参加くださいませ。
『運命の出会いとはこのことか』
EMDR専門カウンセリングルーム ソイル
土持 さやか(つちもち さやか)
そうそう、私が初めてEMDRに出会ったのは今から20年以上前、当時私は家庭裁判所調査官で二度目の沖縄勤務をしていた頃でした。
その頃、臨床心理士の資格は時間外に取っていたので、ポイント取得のために県臨床心理士会の研修を受けたんです。そしてその日の講師が当時琉球大学にいた市井雅哉先生。
テーマはトラウマ治療の症例でEMDR(という当時先進的だった治療!)を紹介するものでした。そこで聞いた症例が衝撃的でした。未成年の頃に冤罪で逮捕され、警察署でひどい取り調べを受けた少年が、大人になってたまたま警察で別のことで事情を聞かれることがあった際、その未成年の時の出来事がフラッシュバックし、逃げようとして警察署の窓から飛び降りようとして、そして市井先生が担当するんです。
当時私は家庭裁判所で少年事件を担当していましたから、「おまえが放火したんだろう!」と刑事から怒鳴られ手錠で取調室の机に縛られる少年が目に浮かびました。(とは言ってもこの事件はもう昭和の昔のことで今はそんなことはないと信じたいですが)で、やっていない少年は、こんな目に合うのは自分が悪いのかもしれないと思い、「僕がやりました」と言ってしまうんです。なんとしてもこの少年への疑いを晴らし尊厳を回復したいと思い、そのあとはのめり込むように研修に聞き入りました。・・・今考えるとトラウマ治療という視点からはちょっとずれていますが(笑)。
この少年はほどなく真犯人が捕まったことで釈放になるのですが、何十年もたった後でフラッシュバックするんですね、そして、そのフラッシュバックや過去の辛い記憶はEMDRという何やら不思議な治療で改善するんです。私の中は感動の嵐でした。
研修後の質問の時間に一番後ろの席から手を挙げました。「この治療はどこに行ったら資格が取れますか?」
市井先生は当時、琉大大学院で夜間この講義をやっていました。この治療と市井先生に会えたのは幸運というしかありません。
そしてすぐに受講を申し込み半年間通いトレーニング終了。40代半ばのことでした。
それからは7年間、とにかく家庭裁判所の中でEMDRを使っていました。非行少年の多くはかつての被害者ですからとても効き目がありました。でもなかなか理解は得られず、そこで1年間早稲田の社会人大学院に通って非行少年へのEMDRの効果に関する論文を書いたんですね。そしてこれから少年の更生プログラムにEMDRを使える、という時に東日本大震災が起きたんです。千年に一度という大災害下にこの治療法が多くの傷ついた人々の回復に役に立つと思いました。
そこから退職して個人相談室を開設しようと大転換です。一所懸命、臨床家資格を目指しました。自分でやっていけるだけの知識と技量が必要だと思いました。(今思うと臨床家取得はやっとそこからがスタートという初歩の初歩だったと思いますが。)とにかく目標があったから頑張れたと思います。大変というよりは張り合いがあり充実していました。厳しい指摘の数々でしたが大先輩方にはこの時大変お世話になりました。
そして2012年に個人相談室を開設しました。おそらく日本で初めて相談室の名前に「EMDR専門」を冠していましたので、ほとんどの方がEMDRを希望されます。月に30~50ケース、その8割に1時間の処理をしたとすると、これまでに5000時間ぐらい指を振りパルサーのスイッチを入れていたことになります。ずいぶんいろいろなケースがありましたが、この治療の効果にどれほど助けられたかと実感します。
というわけで、皆さんもぜひこのEMDRの治療を積極的にどんどん取り入れてほしいと思うんです。自信をもって使えば使うほどいろいろなケースに出会えて経験値が上がり、さらに自信をもってクライアントさんに提案できるし責任をもって使えるようになると思います。
最近つらつらと「トラウマからの回復」って何だろうと思うんですが、色々ある中で私にとっては「尊厳の回復」が大きいんです。そう思ったら、私のスタートはやはりあの日聞いた冤罪の元少年の症例だったんだと思います。EMDRとの運命の出会いに感謝ですね。
武蔵小杉セラピールーム
成井 尚子(なるい しょうこ)
① 今どんなシチュエーションでEMDR臨床していますか?どういう風に役立っていますか?
現在、私設のカウンセリングルームで複雑性PTSDのクライアントを中心に臨床を行っております。
EMDRはそれまでの臨床経験と組み合わせながら使っていける広がりと創意工夫の余地がたくさんある心理療法だと思います。トラウマの場面のある一瞬だけを扱ってトラウマ場面を遠ざけたり小さくしたりいろいろ工夫しながらクライアントへの負担をできるだけ小さくすることができるのでとても使いやすく、複雑性PTSDの方が日常苦しんでいるフラッシュバックの軽減をはかることもでき、編み込みを使うことでトラウマを経験したことで凝り固まってしまったマイナスの考え方のパターンにもアプローチできたりするのでEMDRが使えると本当に心強いです。年齢を問わずさまざまな場面で活用しています。
EMDRの研修を受けてから話の内容ばかりでなく、意識レベルや解離の度合い、自律神経の状態の変化、体の細かい動きなどにも注意を向けて観察するようになり、少しの変化にもそれまでより素早く対応するようになったと感じています。
② 臨床資格を取るのは大変でしたか?過程でどんな体験をしましたか?
EMDRを教わったばかりの頃は、何度もテキストを見てたしかめながらこわごわとやっていて声かけの言葉もぎこちなくなかなかうまく使いこなせなかったりしました。そうかと思えば予想外にうまくいってとても喜んでいただけることもあり、毎回試行錯誤しているような感じでした。これで良いのかと疑問に思うことも多かったため、定期的にスーパーバイズやコンサルテーションを受けながら徐々にEMDRに慣れていきました。資格取得に必要とされている学会の継続研修はちょうどの日常の臨床場面で対応に悩むような難しいケースにすぐ使える技法など役に立つことばかりなので、できるだけ都合をつけて参加するようにしていました。そうやって一歩一歩学んでいく中でケース数も自然と積み重なっていったので、臨床家資格を取るのに特別なことをしたという感じではなかったように思います。
③ 他のEMDR臨床家に伝えたいこと。
おつかれさまです。お互い、時には複雑なケースで大変な思いをしたり悩んだりすることもあったり限度を超えてがんばりすぎてストレスを抱え込んでしまったりすることもあるかもしれません。心と体のケアに気をつけて、末永くご一緒に学んでいけるのを楽しみにしております。今後ともよろしくお願い申し上げます。
④ これから臨床家資格を取ろうか、考えている方へのメッセージ
臨床家資格は一見、敷居が高そうに見えますが、学会の研修は毎回最新の知見が満載で、普段臨床をやっていて壁にぶつかるようなケースにとても役立つのでできるだけ参加されると良いと思いますし、コンサルテーションを受けることでいままで自分が持っていなかった技術や新しい視点が身につきます。資格取得の条件となっていることはどれも日常必要な勉強をして臨床の経験を積んでいけば満たされることばかりなのでみなさまもぜひチャレンジしてみてください。
理事(下線は委員長・委員長以下50音順)
新理事長:市井雅哉
副理事長:菊池安希子
事務局:海野千畝子(理事会) ・檜原広大(社団法人化)・大塚美菜子(IT)
倫理委員会:天野玉記
広報委員会:名和淳・久冨香苗
資格認定・トレーニング委員会:竹内伸・森ゆみ
編集委員会:小林正幸・南川華奈
国際交流委員会:菊池安希子・松本大進
HAP:仁木啓介・岡田太陽
監事(50音順)
上田英一郎・吉川久史
香川大学保健管理センター
大塚 美菜子(おおつか みなこ)
このたび,新たに理事に就任させて頂くことになりました大塚美菜子と申します。役員の業務としてはIT関連を担当させて頂くことになりました。ITの仕事は表には見えにくい領域に該当するかもしれません。ドメインやサーバーの保守・管理,ホームページの記事作成と更新,ML管理,各種申し込みシステムの作成など,スムーズな情報提供,交流のための基盤を維持することが主たる業務の内容となっております。昨今,学会の規模が拡大するに従い,事務局業務の円滑な遂行にあたりアナログからデジタルへの移行が求められる機会も増えて参りました。事務局と連携し新しいシステムの導入を検討したり,法人化を前にして現行システムの内容を再確認したりと奔走する日々を送っております。微力ではございますが,学会の発展に少しでも貢献できるよう努めさせて頂きたく,どうぞ宜しくお願い致します。
そして末筆ではございますが,この場をお借りし,長きにわたりIT担当理事を務められ,これらのシステムの構築から運用・維持に至る業務を一手に担って下さっていた本多正道先生のご尽力に改めて感謝の意を述べさせて頂きたいと思います。
芦屋カウンセリングルーム Root
南川 華奈(みなみかわ かな)
この度、新理事に就任いたしました、南川華奈と申します。微力ではございますが、日本EMDR学会発展のために精進してまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
今回、理事としては大学・大学院時代の恩師でもあります、小林正幸先生の元で編集委員のお仕事を担当させていただきます。
これまでEMDR研究は、臨床に関わる論文が中心に多く投稿されてきました。近年は、EMDRの作用機序に関わる基礎的研究が投稿されるようになってきましたが、日本においては、まだまだEMDRの基礎的研究が不足していると感じています。かく言う私も現在、EMDRの作用機序についてサッカード眼球運動という視点から、鋭意博士論文を執筆中です。編集委員として、皆さんが積極的に論文投稿したいと思えるような学術誌となるよう、励んでいきたいと思います。
さらに、日本で行われている素晴らしい研究が世界のEMDR研究者や臨床家にも目を向けていただけるようにすることが現在、喫緊の課題となっており、その課題にも取り組んで参りたいと思います。
また、私は、これまで学術大会の準備委員や、臨床セミナーや関西EMDR研究会の幹事を担うなど、運営としてもいくつか経験を積んできました。この力は、学会会員の皆様のニーズを把握し、より良い学会となるような全体的な視点で捉える力となっています。この力を還元できるよう、引き続き取り組んでいきます。
個人的な話にはなりますが、数年前、私は「やっぱりEMDRを学んでみたい!」と一念発起し、兵庫教育大学大学院博士課程の門を叩きました。その後、EMDR関連の勉強会やセミナーなどにも参加させていただく中で、まだEMDR臨床超初心者の私を皆さんが優しく迎えて下さいました。そして仲間ができました。
さらに、市井雅哉先生にお供して、国内のみならずEMDR EuropeやEMDRIAにも参加する機会を得て、EMDR Association(インド)では研究発表をさせていただきました。その後も自主的に海外のEMDRに関する学会やワークショップにも参加する中で、日本だけでなく世界のEMDR研究者、臨床家たちが、例えどんなに有名な先生であっても、「EMDRをしている」というだけで、どこでも私を温かく迎え入れてくださったことに本当に感謝しています。
まだ経験も浅く、未熟ではありますが、少しずつ皆さんに恩返しができるよう取り組んで参りたいと思います。EMDR学会が発展し、トラウマで苦しむ多くのクライエントさんに還元できるよう、皆様の協力をどうぞよろしくお願いいたします。
(1)学会賞について
第2回 日本EMDR学会学術大会 研究発表優秀賞
受賞者:佐藤俊介・木村泰博・市井雅哉
発表演題:両側性左右交互の触覚刺激の速度が肯定的な記憶のイメージの鮮明度と感情の強度に与える影響
発表大会:2023年7月21日(金)日本EMDR学会第18回学術大会
第3回 日本EMDR学会学術大会 研究発表優秀賞
受賞者:水口啓吾・三谷綾花・市井雅哉
発表演題:抑うつ傾向者における自伝的記憶の概括化に両側刺激が及ぼす影響―懐かしさ音楽による聴覚刺激との比較を通して―
発表大会:2024年7月7日(日)日本EMDR学会第19回学術大会
(2)大会について
報告
日本EMDR学会第18回学術大会『再びつながる』
日時 2023年7月21日(金)
場所 ラッセホール
継続研修 NEST(Neuroaffective Embodied Self Therapy:
神経感情身体化自己療法)
日時 2023年7月22,23日(土・日)
講師 Sandra Paulsen PhD (サンドラ・ポールセン)
(ポールセン統合心理学研究所)
場所 ラッセホール
日本EMDR学会第19回学術大会『セラピストとしてのあり方を問う
-技法の前にあるもの-』
日時 2024年7月7日(日)
場所 明治大学駿河台キャンパス リバティタワー
継続研修 ADHDやASDといった神経多様性の特徴を持つ子どもへのEMDR
日時 2024年7月27,28日(土・日)
講師 Susan Darker-Smith先生
(イギリス、チャイルド・トラウマセラピー・センター)
場所 オンライン
予告
日本EMDR学会第20回学術大会『「これまで」と「これから」』
日時 2025年7月19,20,21日(土・日・月祝)
継続研修
講師 Natalia Seijo(スペイン、心理療法&トラウマセンター)
https://nataliaseijo.com
報告
2023年3月31日~4月2日にオンラインにてWeekend1トレーニング開催。18名修了
2023年8月11日~13日神戸にてWeekend2トレーニング開催。32名修了
2023年11月10日~12日東京にてWeekend1トレーニング開催。45名修了
2024年3月1日~3日神戸にてWeekend1トレーニング開催。63名修了
2024年10月4日~6日神戸にてWeekend2トレーニング開催。63名修了
2024年11月8日~10日東京にてWeekend1トレーニング開催。63名修了
2024年11月22日~24日新潟にてWeekend1トレーニング開催。27名終了
(能登半島地震支援活動の一環としてJEMDRA-HAP企画、一般募集なし)
予告
2025年3月14日~16日神戸にてWeekend1トレーニング開催
(詳細はこちらをご確認ください)
2023年2024年特大合併号が出来上がりました。原稿をお寄せくださった先生方の珠玉の作品集のようになりました。学会を牽引されてきた先生、トレーニングを受け始めた先生、地方で頑張っている先生、臨床家資格を取得された先生、コンサルタントとしてご活躍される先生、EMDRのマスターとして海外の学会やサミットに参加された先生、新しく理事に就任された先生・・まるでライフステージのような、それぞれのEMDRへの関わりの素晴らしいプロセスを垣間見させていただきました。なんて素敵な学会なのでしょう。また学会が大好きになりました。(J・N)